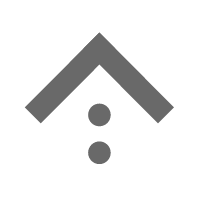紹興の物語(六):猫児橋の由来
猫児橋の由来
紹興城市の北東には石橋があり、猫児橋と呼ばれ、戒汚職橋とも呼ばれている。この橋の由来といえば、興味深い伝説がある。
猫児橋ができる前、川の南西には線香の盛んな大きなお寺があって、ネズミが意外と多いのに、河東ではネズミを見つけることは少なかったと伝えられている。河東に永福親方という孤児の老人が住んでいて、子猫を助けて家に抱いて飼っていたのだ。半年も飼っているうちに、このあたりのネズミはほとんどがそれに飲み込まれてしまった。それを知ったお寺の当主は、永福師匠から猫を借り、三日後に返す約束をした。
その日の夕方、当家の和尚さんは猫を大雄殿に入れて、その猫がどれほどの腕前を持っているのか、自分でドアの外に隠れて見ていた。ネズミたちが声を張り上げて布団に飛びつくと、猫は身を躍らせ、どこへ飛び跳ね、どこまで追いかけてくるのか、ネズミたちを振り回して息を切らすのが目に入った。すると、猫は振り向いて飛びつき、首謀者の大きなネズミにかぶりついた。ネズミはみんな慌てていて、一晩のうちに死んだネズミが大雄殿に横たわっていた。
当家の和尚は、この宝猫をはかり呑んでしまおうと、猫を閉じこめ、推して寺を飛び出したが、見つからず、腹が立って永福親方は何も言えなかった。ある日、当家の和尚さんは、猫に何日もえさをやっていないことをふと思い出して、夜中に冷や飯を持って行ったのだ。扉がやっと隙間をあけたので、猫は逃げ出して、一足飛びに川に飛び込もうとはしなかった。何日か空腹のため、力が足りずに溺死してしまったのである。
永福親方はそれを知って、心を痛めて、もし橋があったら宝猫は死なないと、いつもぶつぶつ言っていました。「橋……猫……猫……橋……」と、重病になった時まで呟いていた。
この話を聞いた当家の和尚はとても恥ずかしくて、永福師匠の死後、過ちを償うことを决めて、自分の長年の蓄えを出して和尚と善男善女に寄付を呼びかけて、橋を建てて、猫児橋と名づけました、後世の人にこの教訓を記憶させるためだ。

- 0575-89180831
- 浙公网安备 33060202000378号 浙ICP备05014601号-1
- Copyright © 2020-2050 绍兴市旅游委员会 版权所有